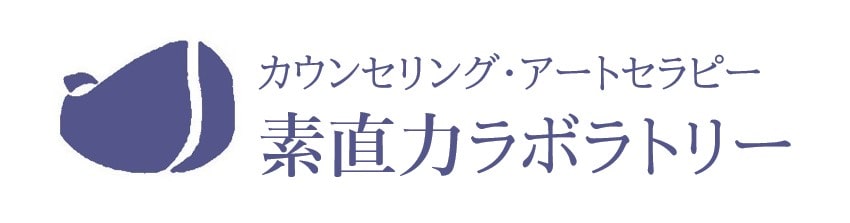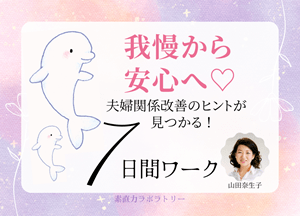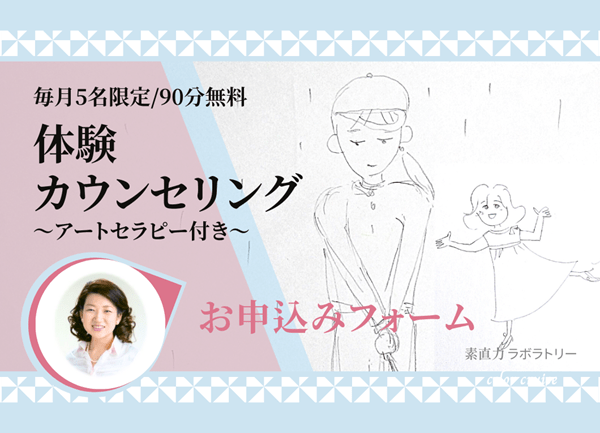離婚で子どもの心に何が起こる?|親ができるサポートと将来への備え
はじめに
親の離婚は、現代では決して珍しいことではありません。けれども、それを経験する子どもたちの心には、大きな変化や葛藤が生まれることがあります。
家庭のかたちが変わることは、子どもの心理面や生活環境、そして将来の見通しにまで影響を及ぼす可能性があります。ただし、その感じ方や反応は一人ひとり異なり、年齢や性格、置かれた環境によって大きく変わってきます。
本記事では、親の離婚を経験した子どもが直面しやすい心の課題や不安について、具体的に解説していきます。さらに、親としてできるサポートのあり方や、将来への備えについても触れながら、子どもたちの健やかな成長を支えるための視点を一緒に考えていきましょう。
親の離婚が子どもに与える影響とは?

親の離婚は、当事者である夫婦だけでなく、子どもにとっても大きな出来事です。子どもは自分で状況を選べない立場にありながら、家族の変化を敏感に感じ取り、その中で心や行動にさまざまな変化を起こすことがあります。
実際、離婚が子どもにどのような影響を与えるのかは、年齢や性格、家庭の状況によって異なります。子どもが受ける影響には心理的なものだけでなく、学校や友人関係、将来の価値観にも関わる社会的な側面も含まれるのです。
離婚が子どもに与える心理的・社会的影響の深刻さ
親の離婚は、子どもにとって人生の転換点となる重大な出来事です。この経験は、子どもの心と生活の両面に影響を及ぼし、たとえば以下のような課題が現れることがあります。
- 学業成績の低下
- 抑うつや不安などの精神的な問題
- 愛着関係の喪失・不安定さ
- アルコールや薬物などの依存傾向
特に注目されているのは、親の離婚を経験した子どもは、将来自身が結婚した際の離婚率が高まる傾向にあるという研究結果です。
ただし、すべての子どもが同じように深刻な影響を受けるわけではありません。年齢や性格、家庭環境によってその反応はさまざまです。
子どもの感情的な反応の多様性
親の離婚に対する子どもの反応は、とても多様です。ある調査では、多くの子どもが「悲しかった」「ショックだった」と答えていますが、一方で「ホッとした」「家庭の空気が変わって嬉しかった」と前向きな反応を示す子どもも一定数います¹。
これは、離婚前の家庭の雰囲気や両親の関係性が、子どもの受け止め方に強く影響していることを示しています。
さらに、「将来への不安を感じた」「経済的な心配がある」と冷静に現実を受け止める子どもも少なくありません。大人が思う以上に、子どもは状況を理解し、柔軟に適応しようとしているのです。
また、約半数の子どもは「大きな問題は感じなかった」と答えており、適応能力の高さも見逃せません¹。
年齢による影響の違い
離婚の影響は、子どもの年齢によって大きく異なります。
たとえば:
● 幼児期(3~6歳)
この時期の子どもは、自分と他者を区別しはじめる発達段階にあります。父親(あるいは母親)の不在に気づき、「どうしていないの?」と繰り返し質問するなど、強い不安感や混乱を示します。
● 小学生
離婚の意味をはっきりと理解するにはまだ難しく、混乱したり、自分のせいだと思い込む子どももいます。特に小学校低学年での離婚経験は、心の発達に大きな影響を与える可能性があります。
● 中高生(思春期)
中高生になると、状況をある程度理解し、冷静に見つめる力が育ってきますが、内面に深い葛藤を抱えることが多くなります。
この時期は、親の支援よりも信頼できる友人との関係が心の支えとなることが多く、同世代のつながりの重要性が増していきます。
なお、調査によると、離婚がもっとも多い時期は小学校低学年の子どもを持つ家庭であることがわかっており¹、この時期の子どもへの配慮と関わり方がとくに重要です。
心理的・精神的な影響

親の離婚は、子どもの心理面に深刻で長期的な影響を及ぼすことがあります。子どもは、不安や罪悪感、怒り、混乱、悲しみなど、複雑でさまざまな感情を同時に抱え、その感情の処理に時間がかかる場合も珍しくありません。
特に重要なのは、これらの心理的な影響が一時的なものにとどまらず、大人になってからも続く可能性があるという点です。
このため、子どもの心の変化に早めに気づき、適切なサポートを行うことが、将来の心の健康を守るうえで非常に大切です。
自責の念と罪悪感
多くの子どもは、親の離婚の原因を自分のせいだと考えてしまう傾向があります。
(「ぼく、何か悪いことしたのかな…」と戸惑いながらも、実は「お父さんもお母さんも助けたい」と心のどこかで願っている子もいます。)
これは、子どもの発達段階における自己中心的な思考パターンによるもので、「自分が良い子でなかったから」「自分のせいで両親が喧嘩した」などと感じることが少なくありません。
また、離婚のストレスや感情のもつれから、一部の親が無意識に子どもを責めてしまうこともあります。
これは決して子どものせいではなく、親自身の葛藤の表れであり、子どもの心に深い傷を残す原因となります。
このような自責の念は、子どもの自尊心を大きく傷つけ、将来的な人格形成にも悪影響を及ぼす可能性があります。
(「どうして僕だけがこんなに責められるんだろう…」と心を閉ざしてしまう子もいます。)
さらに、調査では、離婚を経験した子どもの半数以上が、自分の希望や意見を十分に聞いてもらえなかったと感じていることが明らかになっています¹。これは、子どもの無力感や自責感を強める要因の一つです。
その結果、離婚経験のある子どもは、自分の言動に過剰な責任を感じ続けたり、大人や社会に対する不信感を抱いたりすることもあります。
(「どうせ僕の気持ちはわかってもらえない…」そんな孤独を感じているかもしれません。)
だからこそ、大人は子どもに責任を押し付けるのではなく、「離婚は子どものせいではない」ということをしっかりと伝え、安心感を与えることが重要です。
愛着の問題と人間関係への影響
親の離婚は子どもの愛着形成に重大な影響を与えます。
子どもは「親に捨てられたのかな…?」と不安や孤独を感じ、両親からの愛情を信じることが難しくなることがあります。
これは将来的な人間関係においても影響し、恋愛や結婚生活で「また裏切られるのでは」と相手を信じられなかったり、見捨てられることを恐れたりすることにつながることがあります。
(「どうしていつも一人ぼっちなんだろう…」そんな孤独を抱える子も少なくありません。)
また、離婚によって育った家庭を失った喪失感や否定感から、自分は何者なのかというアイデンティティの確立に悩む子どももいます。
(「ぼくはこの家の子じゃないのかな…」と感じることもあるでしょう。)
しかし、両親が離婚後も協力して子どもと関わり、愛情を伝え続けることができれば、子どもの自尊心や自己肯定感は育ちやすくなります。
(「ママもパパも、ぼくのことをちゃんと見てくれているんだ」と安心できると、心が少しずつほぐれていきます。)
精神的不安定と問題行動
親の離婚による精神的ストレスは、子どもの行動面にも様々な影響を与えます。
約2割の子どもが精神的不安定を感じており、これが学業成績の低下や不登校、生活リズムの乱れなどの問題として現れることがあります。
(「学校に行くのが怖い…」「朝起きられないよ…」とつらさを抱える子もいます。)
また、強い寂しさや孤独感から、依存症などの問題行動に走る子どもも少なくありません。
(「さみしくてついゲームやスマホばかり触ってしまう…」そんな苦しみを抱える子もいます。)
欧米の研究では、離婚後も続く両親の葛藤が子どもの心の安定や成長に深刻な影響を与えることが指摘されています。
「コペアレンティング」とは、離婚後も両親が協力して子どもの育児や養育に関わることを指します。
日本でも同様に、離婚後の両親の対立や争いが続く「葛藤的なコペアレンティング」は、子どもの行動上の問題と関係している一方で、
お互いに尊重し協力し合う「協力的なコペアレンティング」は、子どもの適応や成長を支える重要な要素であることがわかっています。
縦断調査の結果からも、離婚後の両親の葛藤が子どもの問題行動を高める可能性が示されており、両親の関係性の改善が子どもの心身の健康保持にとって極めて重要です。
(「パパとママがケンカしないでほしい…」子どもはただそれだけを願っています。)
生活環境の変化と経済的影響

親の離婚は子どもの生活環境に劇的な変化をもたらします。
住居の変更や学校の転校、生活リズムの変化など、子どもを取り巻くあらゆる環境が影響を受ける可能性があります。
特に経済的な影響は深刻で、多くのひとり親家庭が経済的困難に直面しています。
これが子どもの生活の質や将来の選択肢に大きく影響することも少なくありません。
生活水準の低下と経済的困難
調査によると、約4割の子どもが両親の別居により生活が苦しくなったと回答しており、離婚による経済的影響の深刻さが浮き彫りになっています¹。
特に問題なのは、日本では約84%の子どもが養育費を受け取っていないという現実です。
この経済的困難は、子どもの教育機会や習い事、進学選択などに直接的な影響を与え、将来の可能性を制限する要因となります。
(「「習い事は続けたいけど、どうなるんだろう…」そんな不安を感じる子もいます。)
ひとり親家庭の経済的困難は、子どもの日常生活にも様々な形で現れます。
食事の質の低下や衣類・学用品の購入が難しくなったり、友人との交流の機会が減ったりすることがあります。
(「みんなと同じものが用意できなくて、恥ずかしい…」と感じる子もいるでしょう。)
こうした経済的制約は、子どもの自尊心に影響を与え、将来への不安を増大させることがあります。
だからこそ、適切な養育費の支払いや公的支援制度の活用が重要です。
(「みんなと同じチャンスがほしい…」そう子どもたちは心から願っています。)
住環境と学習環境の変化
離婚に伴う住居の変更は、子どもにとって大きなストレス要因となります。
慣れ親しんだ環境を離れることで、安心感や安定感を失い、新しい環境への適応に時間がかかることがあります。
(「また引っ越し?友だちと離れるのはさみしいな…」と感じる子もいます。)
特に、転校を伴う場合は、新しい学校での人間関係の構築や学習環境への適応が必要となり、子どもにとって二重の負担となります。
学習環境の変化も見逃せない問題です。
経済的困難により、学習塾や習い事を続けることが難しくなったり、家庭内で学習をサポートする大人の時間が減少したりすることで、学業成績に影響が出る可能性があります。
また、家庭内の不安定な状況が集中力の低下を招き、学習への意欲を削ぐこともあります。
こうした課題に対しては、地域や学校、行政による学習支援や心のケアが、子どもたちの安心と学びを守る重要な役割を果たします。
日常生活のリズムと安定性の喪失
親の離婚により、子どもの日常生活のリズムが大きく変化することがあります。
片親との生活になることで、これまでの生活パターンが維持できなくなったり、親の働き方の変化によって家族と過ごす時間が減少したりすることがあります。
また、両親の家を行き来する面会交流がある場合、週末や休日の過ごし方も変化し、子どもにとって日々の予測可能性が低くなることも少なくありません。
(「今日はどっちの家に帰るんだっけ…?」と不安を感じる子もいます。)
生活の安定性の喪失は、子どもの心理的な安定にも影響を及ぼします。
特に、離婚後も両親の葛藤が続いている場合、子どもは常に緊張状態に置かれ、安心してリラックスできる時間が減ってしまいます。
調査では、生活リズムの乱れや不登校などの問題も報告されており、こうした変化が子どもの心身の健康に及ぼす影響は決して小さくありません。
安定した日常生活のリズムを早期に整えることが、子どもの適応と回復を支える重要な要素となります。
親子関係と面会交流の課題

親の離婚後、別居親との関係維持は大きな課題です。
日本では約70%の子どもが別居親と面会できていないとされ、子どもの心に寂しさや不安を残す要因となっています。
面会交流は法的に取り決められていても、実際の実施が難しいことも多く、子どもの意思が十分に尊重されないケースも見られます。
「どちらの親にも愛されている」と感じられる関係づくりが、子どもの安心と成長にとって重要です。
別居親との関係断絶の影響
調査によると、別居後すぐや2~3年後でも、別居親と自由に連絡をとれない子どもが約半数にのぼります²。
この関係の断絶は、子どもにとって大切な愛情源の喪失であり、自尊心やアイデンティティの形成に深刻な影響を与えることがあります。
特に、日本では父親が別居親となることが多く、父親の役割モデルの不在が子どもの発達に影響する可能性も指摘されています。
(「お父さんはもう僕に会いたくないのかな…」と感じる子もいます。)
また、別居親の情報がないまま成長すると、子どもの中で理想化や否定的なイメージが形成され、現実的な親子関係の再構築が難しくなることもあります。
定期的な面会交流や共同養育が実現されることで、こうした心理的負担は軽減され、子どものメンタルヘルスや信頼関係の回復に寄与することが期待されています。
子どもの意思と大人の判断の狭間
面会交流において、最も扱いが難しい問題のひとつが「子どもの意思」です。
実際には、子どもが同居親や弁護士など周囲の大人の影響を受けて、「別居親に会いたくない」と話すこともあり、本当の気持ちが見えにくくなることがあります。
けれども、子どもの意思は単純ではなく、その時々の状況や気持ちの変化に左右されやすいものです。
一時的に不安や混乱から否定的な気持ちを抱いていたとしても、時間と環境によって変わっていくことも珍しくありません。
(「会いたくないって言ったけど、本当は少しだけ会いたいかも…」と心の中で揺れている子もいるかもしれません。)
大切なのは、子どもに責任を負わせないこと。
そして、大人が子どもの言葉の背景にある気持ちをくみ取りながら、長期的な視点で最善の利益を考えることです。
たとえ取り決めがあっても、子どもが本心をうまく表現できないこともあります。
だからこそ、専門家のサポートを受けながら丁寧に判断していく姿勢が求められます。
注釈
「子どもにとっての最善の利益(best interests of the child)」という考え方は、家庭裁判所や児童福祉の現場でも国際的に重視されている視点です。
また、「会いたくない」と言う子どもが葛藤の中で本心を隠していることも多いため、早急な判断は避け、環境を整えながら見守ることが大切です。
面会交流支援の必要性と実践
親の離婚後、別居親との面会交流を実現し継続するためには、専門的なサポートが欠かせません。
特定非営利活動法人ウィーズ(https://weez.jp/)では、子どもの視点に立った「面会交流支援」を無料で提供し、別居親と会う機会の調整や、両親間の感情的な対立の緩和に取り組んでいます。
こうした支援によって、子どもの利益を最優先にした面会交流が可能になります。
面会交流支援では、子どもの年齢や発達段階、家族の状況に応じたきめ細かな配慮が求められます。
面会の頻度や方法も、子どもの負担にならないよう調整することが大切です。研究によると、父母が協力して別居親との交流を促進すると、子どもの心理的な苦痛やメンタルヘルスの問題が軽減されることが示されています。
また、ウィーズが運営する「みちくさハウス」のような一時利用型施設は、子どもが安心して過ごせる場所として、心身の安全と安定を支える重要な役割を果たしています。
社会的支援と専門的ケアの重要性

親の離婚による子どもの課題は家庭だけでは解決しづらく、社会全体の支援が必要です。専門家による継続的なサポートや、オンライン・対面を組み合わせた多様な支援体制が、子どもの健やかな成長を支えます。これにより、安心して未来へ進める環境づくりが期待されます。
心理的サポートと専門的介入
離婚を経験した子どもには、専門的な心理サポートが不可欠です。
カウンセリングや心理療法を通じて、感情の整理や健康的な心のケアが可能になります。
特に、自責感や将来不安といった複雑な感情への対応には専門家の介入が効果的です。
年齢や発達段階に応じた療法が重要で、幼児期には遊戯療法、思春期には対話を中心とした認知行動療法が適しています。
家族療法によって残された家族関係の修復や新しい家族構造への適応も支援できます。
継続的な専門ケアが、子どもの精神的回復と健全な成長を支えます。
教育支援と学習環境の整備
離婚家庭の子どもたちに対する教育支援は、将来の可能性を広げる大切な取り組みです。
経済的困難があっても、学習機会を確保することで子どもたちの成長を支えます。
単なる学習指導にとどまらず、子どもの話に耳を傾け、心理的サポートを行うことも重要です。
親の不仲や面会交流の悩みなど、多面的な支援を通じて、子どもたちの価値観や立場を尊重しながら寄り添う姿勢が求められます。
オンラインとオフラインの包括的支援
現代の支援では、オンラインとオフライン双方のアプローチが効果的です。
特定非営利活動法人ウィーズのLINE相談窓口は、子どもたちが気軽に相談できるオンライン支援として重要な役割を担っています。
これにより、地理的・時間的な制約を越え、必要な時にすぐサポートを受けられます。
一方で、「みちくさハウス」などの一時利用型施設は、物理的な安心と安全を提供するオフライン支援として欠かせません。
子どもたちが直接訪れて相談できる環境が、信頼関係の構築を促します。
このようにオンラインとオフラインを組み合わせることで、多様なニーズに対応しつつ、子どもたちの心身の安全を守り、健全な自立を支える包括的な支援体制が実現します。
「家庭が崩れそうな時でも頼れる存在がいる」という安心感を提供することが可能になるのです。
将来への影響と長期的な視点

親の離婚が子どもに与える影響は、一時的なものにとどまらず、成人後の人生にも及ぶ可能性があります。
結婚観や家族観の形成、人間関係の築き方、心理的健康など、多方面で長期的な影響が見られることが研究で示されています。
しかし、適切な支援と理解があれば、これらの影響を最小限に抑え、むしろ子どもの成長や自立の機会として活かすことも可能です。
長期的な視点で支援を行うことが、子どもが健やかに未来を築くために重要となります。
成人後の結婚観と家族観への影響
親の離婚を経験した子どもは、将来の結婚生活に特有の課題を抱えることがあります。
統計的には、離婚経験のある子どもは、成人後の離婚率が高くなる傾向があり、これは結婚に対する不安や信頼関係の構築の難しさが影響していると考えられています。
また、「結婚は壊れるもの」という認識から、長期的なコミットメントに対する恐怖感を持つ場合もあります。
一方で、調査によると約7割の人が両親の離婚をポジティブに捉えていることもわかっており、すべての子どもが否定的な影響を受けるわけではありません。
むしろ、離婚を通じて健全な家族関係の大切さを学び、自身の結婚生活でより慎重で思慮深い態度を持つ人も多くいます。
重要なのは、離婚経験から得た学びを建設的に活かし、より良い人間関係を築く力を育むことです。
心理的レジリエンスと適応能力の発達
親の離婚という困難な経験は、子どもの心理的レジリエンス(回復力)を高めることもあります。調査では、家族関係に対する恥ずかしさの軽減や自立心の向上など、ポジティブな変化を感じる子どもが多いことが明らかになっています。
困難を乗り越える経験を通じて、将来の課題に柔軟に対応できる適応能力や強い精神力を育むことができます。
実際、両親の離婚を肯定的に捉える子どもが多いという調査結果は、彼らの高い適応力を示しています。
冷静に事実を受け止め、状況を客観的に見る力が身につくことで、将来の困難にも上手に対処できるようになるのです。
このような心理的成長は、親の離婚を経験した子どもたちが得ることのできる大切な財産と言えるでしょう。
社会的な制度改善への期待
親の離婚を経験した子どもたちの長期的な健全な成長を支えるには、社会制度の改善が不可欠です。
特に、共同親権制度に関しては賛否が分かれており、子どもの最善の利益を最優先に考えた制度設計が求められています。
養育費の確実な支払い体制や面会交流支援の充実も重要な課題です。
さらに、離婚後の共同養育を支援する専門機関の強化や、離婚家庭の子どもへの教育支援制度の拡充も必要です。
社会全体が偏見や差別をなくし、離婚家庭の子どもたちを積極的に支える意識を持つことで、誰もが安心して成長できる環境が整います。
将来的には、離婚がネガティブなイメージや偏見の対象とならず、多様な家族形態の一つとして社会に受け入れられることが期待されます。
まとめ
親の離婚を経験した子どもたちが直面する課題は、心理的、社会的、経済的な側面において多岐にわたり、その影響は長期間にわたって続く可能性があります。
しかし、本記事で詳しく検討してきたように、適切な支援と理解があれば、これらの課題を乗り越え、むしろ成長の機会として活用することも可能です。
最も重要なのは、子どもたちの声に耳を傾け、彼らの立場に立って考えることです。
調査結果からも明らかなように、子どもたちは大人が想像する以上に現実を理解し、適応する能力を持っています。
しかし、その過程で必要な支援を受けることで、より健全で前向きな発達が可能になります。
(「つらいときもあるけれど、今頑張ればきっと自由になれる」そんな前向きな気持ちを抱く子どもたちがいます。)
社会全体としては、離婚家庭の子どもたちに対する偏見をなくし、多様な家族形態を受け入れる寛容な環境を整備することが求められています。
専門的な支援システムの充実、教育機会の保障、経済的支援の拡充など、多方面からの総合的なアプローチにより、すべての子どもたちが健やかに成長できる社会の実現を目指していく必要があります。
親の離婚は確かに子どもにとって大きな試練ですが、適切な支援があれば、それを乗り越えてより強く成長することが可能です。
よくある質問
親の離婚は子どもに深刻な影響を与えるのでしょうか
親の離婚は子どもにさまざまな影響を与える可能性がありますが、必ずしも深刻な結果を招くわけではありません。
子どもの年齢や性格、家庭環境によって感じ方や反応は異なり、適切な支援や理解があれば、多くの場合、困難を乗り越え、成長の機会とすることができます。
親の離婚により子どもの心理的な問題が生じることはありますか?
親の離婚は、子どもの心理面に深刻で長期的な影響を及ぼすことがあります。
子どもは不安、罪悪感、怒り、混乱、悲しみなどの複雑な感情を抱くことが多く、自尊心の低下や人間関係への不信感など、将来にわたる課題が生じる可能性もあります。
ただし、専門的なサポートや適切な環境があれば、これらの影響を和らげ、子どもが健やかに成長する助けとなります。
親の離婚は子どもの生活にどのような変化をもたらしますか?
親の離婚は子どもの生活環境に大きな変化をもたらします。
住居の変更や学校の転校が必要になることが多く、生活リズムや安定感が乱れることがあります。
また、経済的な負担が増えることで、教育や習い事の機会が減少し、将来の選択肢に制約が生じる場合もあります。
しかし、適切な支援や周囲の理解があれば、子どもはこうした変化に順応しやすくなります。
親の離婚後、子どもと別居親との関係を維持することは重要ですか?
親の離婚後も別居親との関係を維持することは、子どもの健全な成長にとって非常に重要です。
別居親との面会交流が難しいと、子どものアイデンティティ形成や自尊心に悪影響を及ぼすことがあります。
そのため、専門的な支援機関による面会交流の調整や、両親が協力して子育てを行うコペアレンティングが、子どもの心理的安定と成長を支えるうえで大切な役割を担います。
¹厚生労働省『令和3年度 全国ひとり親世帯等調査』、日本財団『18歳意識調査』(第37回)、親子関係支援センター「子どもの離婚意識アンケート」より(一部要約・編集)
² 出典例:特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ「離婚と面会交流に関する実態調査」(2022年)、家庭問題情報センター『家族と法』など。
🌸 「この記事、ちょっと当てはまるかも…」と思ったあなたへ 🌸
ひとりで抱えず、話してみませんか?
ランキングに参加しています。