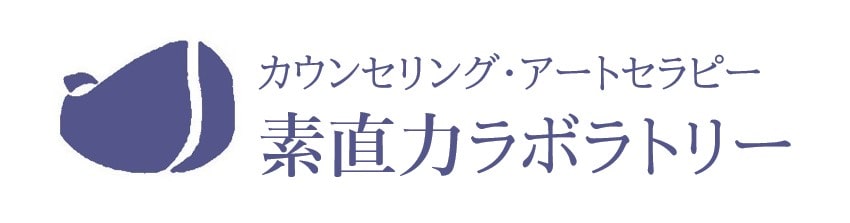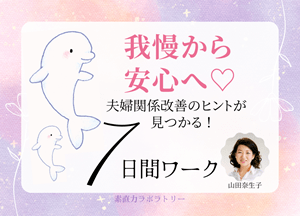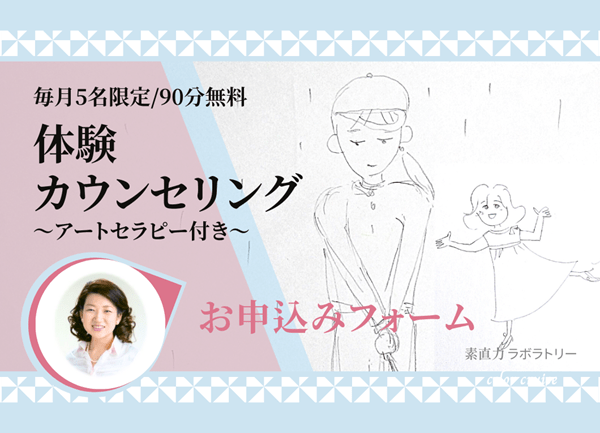夫婦の意識と変わる仕事の価値観〜男女が共に歩む新しいパートナーシップの形とは?
はじめに
現代の日本社会では、「仕事に対する価値観」が男女のあいだで、大きな転換期を迎えています。
長年根強く残ってきた「男は仕事、女は家庭」といった性別役割の意識は、少しずつ揺らぎはじめ、共働き世帯の増加とともに、家庭や社会に新たな課題や可能性をもたらしています。
価値観変化の背景
こうした価値観変化の背景には、まず経済的な事情があります。
特に35~54歳の男性における平均給与の減少は顕著であり、もはや「夫一人の稼ぎだけでは暮らせない」という家庭が珍しくなくなってきました。
このような現実が、これまでの働き方や家族内の役割に対する考え方を見直すきっかけとなっています。
同時に、女性たちのキャリアに対する意識も大きく変化しています。
「子どもができても、仕事は続けたい」と考える女性は年々増加し、平成12年から令和元年にかけて、その割合は着実に伸びています。
女性たちの社会参画への意欲は、今や一過性のものではなく、当たり前の選択肢となりつつあるのです。
現代社会の課題
しかしながら、こうした意識の変化が、実際の行動に結びついているかというと、そうとは言い切れません。
たとえば共働き家庭においても、夫の9割弱が「家事をまったくしていない」という調査結果があります。
この数字は、いまだに家事や育児が「女性の仕事」とされている現実を物語っています。
企業側が育児支援や働き方改革を進めたとしても、家庭内の意識が変わらなければ、女性の負担は減らず、キャリアを断念するケースも後を絶ちません。
このような「外の変化」と「家の中の変化」のギャップこそが、真の男女共同参画社会の実現を阻んでいる最大の壁なのです。
世代間の違い
さらに注目すべきは、世代による価値観の違いです。
たとえばZ世代の若者のあいだでは、「仕事よりも自分や家族との時間を大切にしたい」と考える傾向が強まりつつあります。
特に女子学生の中には、「自信がないから」「両立できる気がしないから」と、結婚や子育てに慎重な姿勢を見せる人が増えています。
一方で、男子学生の中には「子育てについて考えたことがない」と答える人も少なくなく、家庭に対する意識や準備の差が、男女間で依然として存在しているのが現状です。
このような世代間・性別間の意識のギャップを丁寧に理解し、向き合っていくことが、今後の社会政策や企業戦略において欠かせない視点となっていくでしょう。
夫の職業意識の変化とその影響

近年、夫の「仕事に対する意識」が大きく変化しており、それに伴って家庭の経済状況や夫婦関係にもさまざまな影響が生じています。
従来の「夫が家計を支える存在」という概念が揺らぎはじめ、夫婦が共に支え合う新たな家庭経済のかたちが模索されるようになっています。ここでは、こうした変化の背景と、それが家庭にもたらす社会的影響について考えてみましょう。
収入減少の現実
男性の収入減少は、もはや一時的な現象ではなく、統計的にも明確な傾向として表れています。
とくに働き盛りとされる35〜54歳の男性における平均給与の減少は深刻で、これまで「夫の収入で家計をまかなう」ことが当然だったモデルが通用しなくなりつつあります。
このような現実は、家庭の生活スタイルの見直しを余儀なくし、妻の就業継続や復職を促す要因にもなっています。
背景には、日本経済の長期的な停滞、企業の人件費削減、非正規雇用の拡大といった構造的な要因が存在します。
これにより、かつては安定の象徴とされていた終身雇用や年功序列といった仕組みが機能しにくくなり、夫婦がともに働くことが、今や「選択」ではなく「必要」とされる時代に移り変わっているのです。
働き方に対する意識変化
夫の職業意識の変化は、単なる収入の問題にとどまりません。
働き方改革の推進や長時間労働の是正といった社会の動きにより、男性の間にも「仕事以外の時間」――家族との時間や自分の時間――を大切にしたいという価値観が広がりつつあります。
この変化は、家事や育児への参加意識の高まりと直結する可能性を秘めています。
「もっと家庭に関わりたい」と願う男性は確実に増えており、家庭での役割分担にも見直しの兆しが見えはじめています。
とはいえ、理想と現実には大きなギャップが存在しています。
「参加したいけれど、どう関わればよいかわからない」「職場での立場がそれを許さない」といった戸惑いや葛藤を抱える男性は少なくありません。
このギャップは、従来の社会的期待や職場文化と、個人の価値観の狭間で揺れる、現代男性の複雑な立場を映し出しています。
家庭内役割分担への影響
夫の職業意識の変化は、家庭内の役割分担にも少しずつ影響を与えはじめています。
夫婦のどちらかが主導するのではなく、家計も家事も「一緒に支え合うもの」という意識へのシフトが、特に共働き家庭の中で広がりつつあります。
とくに、妻の収入が家計に占める割合が高くなるにつれて、性別に基づく役割分担の見直しが求められるようになっています。
こうした中で、夫婦間のコミュニケーションや協力体制の再構築が欠かせない課題となっています。
しかし、この変化は決してスムーズなものではありません。
男性のなかには「家計の主導権を手放すこと」への不安や、家事・育児スキルの不足からくる戸惑いを感じる人も多く見られます。
また妻の側も、「任せたいけれど任せきれない」「どう伝えればいいかわからない」といった葛藤を抱えることがあります。
こうしたすれ違いや不安を乗り越えるには、家庭内での対話と理解が不可欠です。
互いの価値観や役割意識の違いを認めながら、柔軟に調整していく力が、これからの夫婦に求められていくでしょう。
女性のキャリア形成と男女格差

女性のキャリアを取り巻く環境はこの数十年で大きく変化してきましたが、依然として多くの課題が横たわっています。
雇用形態、昇進機会、賃金水準といったさまざまな側面において、男女間の格差は今なお根強く存在しており、真の意味で女性が活躍できる社会を実現するためには、包括的かつ継続的な取り組みが求められています。
ここでは、現状の課題とその改善に向けた動きを検討します。
雇用形態における格差
女性のキャリアにおいて、特に顕著なのが雇用形態における格差です。
現在でも、女性の非正規雇用率は男性に比べて高く、出産や育児を経て復職する際に正規雇用へ戻るのが難しいという現実があります。
この傾向は、女性の正規雇用率が年齢とともに大きく下がる「L字カーブ」にも象徴されています。
第1子出産後の就業継続率を見ても、正規雇用や自営業では比較的高い水準が保たれている一方で、パート・派遣といった非正規雇用では約4割にとどまっています。
このような格差は、雇用の安定性や福利厚生の有無が、女性のキャリア継続に与える影響の大きさを物語っています。制度的な改善が急務であることは明らかです。
キャリア継続への意識変化
一方で、女性のキャリアに対する意識は着実に変わりつつあります。
令和4年の調査では、20代から40代の女性のおよそ6〜7割が「子どもができても、ずっと働き続けたい」と回答しており、キャリア継続への強い意志が感じられます。
これは、女性たちが社会の一員として自立し、役割を担いたいと願う積極的な姿勢を反映しています。
また、「子どもが大きくなったら再び働きたい」と考える女性の割合は減少傾向にあります。
一度キャリアを中断することの「デメリット」や「将来的な影響」を、より多くの女性が現実的に捉えるようになってきているのです。
その結果として、「辞めずに働き続ける」という選択をする女性が増えてきています。
仕事と家庭の時間配分
男女のキャリア形成における大きなハードルのひとつが、時間の使い方の違いです。
男性は有償労働に多くの時間を費やしているのに対し、女性は家事や育児などの無償労働に多くの時間を割いています。
とくに子育て期の女性は、仕事と家庭の両立において非常に大きな負担を抱えがちです。
この不均衡を解消するためには、男性の家事・育児参画を一層促進するとともに、職場における働き方そのものを見直す必要があります。
たとえば、長時間労働の是正やフレックスタイム制度、テレワークの導入といった柔軟な働き方の推進が、男女双方のキャリアと家庭の両立を支える鍵となるでしょう。
Z世代の価値観と将来展望

Z世代の若者たちは、従来世代とは大きく異なる仕事観や家庭観を持っています。
デジタルネイティブとして育ち、多様性を尊重する彼らの価値観は、今後の社会構造に大きな変化をもたらす可能性があります。
ここでは、Z世代の特徴的な価値観と、それが社会に与える影響について詳しく見ていきましょう。
共働き志向の高まり
Z世代の大学生の間では、共働きを希望する割合が年々増加しています。
特に男子学生の共働き志向の上昇が顕著です。
その背景には、「一人の収入だけでは生活が成り立たない」という経済的な不安が根強くあります。
従来の「男性が稼ぎ、女性が家庭を守る」という性別による役割分担のモデルは、もはや現実的に維持が困難であることを、Z世代は敏感に感じ取っています。
興味深いのは、女子学生の共働き希望理由にも変化が見られる点です。
以前は「仕事を通じた自己実現」や「生きがい」といった理想的な動機が中心でしたが、近年では「夫婦で安定した生活基盤を築くため」といった実用的な理由が目立つようになっています。
この変化は、Z世代のリアリズムや将来不安の反映といえるでしょう。
ワークライフバランス重視
Z世代の特徴として、「仕事よりも家族や自分の時間を大切にしたい」という傾向が顕著に見られます。
これは、仕事中心だった従来の価値観とは大きく異なり、「人生における多様な価値のバランス」を重視する新たな働き方への意識の高まりを示しています。
Z世代にとって、仕事は人生の一部に過ぎず、「すべて」ではありません。
この価値観の変化は、企業の人材確保戦略にも影響を与えています。
長時間労働や過度な責任を求める従来型の働き方では、優秀なZ世代人材を惹きつけることは難しくなっており、多くの企業が柔軟な働き方や福利厚生の充実を進めています。
家庭観の多様化
Z世代の家庭観は、従来世代に比べて大きく多様化しています。
専業主婦を希望する学生は減少しており、「女性が家を守るべき」といった性別役割への固定観念は薄れつつあります。
代わって、男女が対等に支え合う共働きスタイルを理想とする傾向が強まっています。
ただし、理想と現実の間にはギャップも存在します。
たとえば、女子学生の中には、「育児をうまくやれる自信がない」と感じ、結婚や子どもを持つことに対して慎重になる人もいます。また、男子学生の中には、子育てに対して具体的なイメージを持っていない人も少なくありません。
このように、男女間での意識のズレや準備不足といった課題も見え隠れしています。
企業と社会の対応策

男女の仕事観の変化に対し、企業や社会がどのように対応していくかは、今後の日本社会にとって極めて重要な課題です。
従来の価値観や慣習にとらわれることなく、新しい時代に即した働き方や環境整備が求められています。
ここでは、企業や社会が取り組むべき具体策を整理します。
企業の意識改革
企業は、男女の働き方や価値観の変化を正しく受け止め、柔軟な組織運営を進めることが急務です。
これまでの「男は外で働き、女は家庭を守る」といった性別による役割分担の考え方は、すでに時代にそぐわないものとなっており、企業においても価値観の転換が強く求められています。
とはいえ現実には、年配の男性経営層や一部の女性社員の中に、依然としてこの旧来の意識を引きずり、変化をあきらめてしまっているケースも少なくありません。
企業はまず、自社に根付いた古い価値観や当たり前とされてきた風土を丁寧に見直すことから始める必要があります。
具体的には以下のような取り組みが有効です:
- 採用・昇進におけるジェンダー平等の徹底
- 育児・介護支援制度の充実
- テレワークやフレックスタイムなど柔軟な働き方の導入
- 管理職層へのダイバーシティ研修の実施
- 女性管理職の積極的登用とロールモデルの育成
働き方改革の推進
男女ともに働き続けやすい環境を整えるためには、働き方そのものの見直しが必要です。
特に長時間労働の是正は、女性のキャリア継続支援だけでなく、男性の家事・育児参加を可能にする鍵でもあります。
効果的な施策としては:
- 残業時間の削減と生産性向上の工夫
- 有給休暇の計画的取得の促進
- フレックスタイム制度や時短勤務制度の拡充
また、労働組合が企業と従業員の橋渡し役として機能することも期待されます。
従業員の声をすくい上げ、より良い職場環境づくりに活かすことが、持続可能な改革の実現に不可欠です。
社会全体のサポート体制
「子育ては母親だけが担うものではなく、社会全体で支え合うべきだ」という考え方が徐々に浸透してきています。
この考えを実現するためには、保育施設や子育て支援サービスなどの社会的な基盤整備が欠かせません。
- 保育所や学童保育の受け入れ枠拡大
- 地域ぐるみでの子育て支援制度の整備
- 祖父母など家族以外のサポートも得られる環境づくり
経済的に支える夫(妻)と専業主婦(主夫)という家庭のかたちも尊重されています。
夫婦が話し合い、納得のうえでふたりの理想的な役割分担を決めるのも一つの選択です。
社会がさまざまな家族のかたちを認め合い、個々の選択を尊重することが、男女共同参画の実現につながります。
| 対応策の分類 | 具体的な取り組み | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 企業制度 | 育児支援制度、柔軟な勤務形態 | 女性のキャリア継続支援 |
| 働き方改革 | 長時間労働是正、有給促進 | 男性の家事・育児参画促進 |
| 社会保障 | 保育所充実、学童保育拡充 | 子育て負担の社会分散 |
| 意識改革 | 研修、啓発活動 | 固定観念の払拭 |
まとめ
仕事に対する価値観の男女格差は、現代日本社会が直面する重要かつ複雑な課題です。
経済状況の変化や女性のキャリア形成意識の高まり、さらにZ世代の新しい価値観の台頭など、多様な要因が絡み合い、従来の性別役割分担の意識を大きく揺るがしています。
特に夫の職業意識の変化は家庭経済に直接影響を与え、共働きの必要性が一層高まっています。
しかし、意識の変化と実際の行動には大きなギャップがあり、男性の家事・育児への参加率は依然として低い水準にとどまっているのが現状です。
この矛盾を解消するためには、企業の制度改革や社会全体の支援体制の充実に加え、個人の意識改革が不可欠です。
また、Z世代の価値観は将来の社会構造に大きな影響を及ぼす可能性を秘めています。
共働き志向やワークライフバランスの重視、多様化した家庭観は、従来の働き方や社会制度に新たな変革を迫っています。
企業や社会はこれらの変化に柔軟に対応し、包括的な施策を講じることで、真の男女共同参画社会の実現を目指していく必要があります。
よくある質問
男女間の価値観の違いはどのように現れているのですか?
男女の価値観の違いは、共働き世帯の増加や女性のキャリア意識の高まり、そしてZ世代の新しい働き方への志向など、さまざまな形で表れています。特に男性の収入減少により、「男性が稼ぎ、女性が家庭を守る」という従来の役割分担意識が変化し、家事や育児への男性の参加が重要な課題となっています。
企業はどのように対応すべきですか?
企業には、時代の変化に応じた意識改革や具体的な取り組みが求められます。男女平等な採用・昇進の推進、育児支援制度の充実、柔軟な働き方の導入などを通じて、女性の活躍を後押しすることが大切です。また、長時間労働の是正や有給休暇の取得促進など、働き方改革への取り組みも不可欠です。
Z世代の価値観はどのように変化しているのですか?
Z世代の学生は、従来の仕事中心の考え方とは異なり、家族や自分の時間を大切にする傾向が強まっています。共働きを希望する割合も高く、専業主婦を望む学生は減少しています。男女対等なパートナーシップを理想とする意識も広がり、家庭観の多様化が進んでいます。これらの変化は、将来の社会構造に大きな影響を与える可能性があります。
社会全体でどのような対応が必要ですか?
子育ては社会全体で支えるべきという考えのもと、保育所や学童保育の充実など、包括的な支援体制の整備が求められます。また、専業主婦(主夫)という家族のかたちも改めて注目され、多様な選択肢の一つとして尊重されるようになってきています。こうした多様な家族形態や働き方を社会が受け入れることが、男女共同参画の推進につながります。
🌸 「この記事、ちょっと当てはまるかも…」と思ったあなたへ 🌸
ひとりで抱えず、話してみませんか?
ランキングに参加しています。