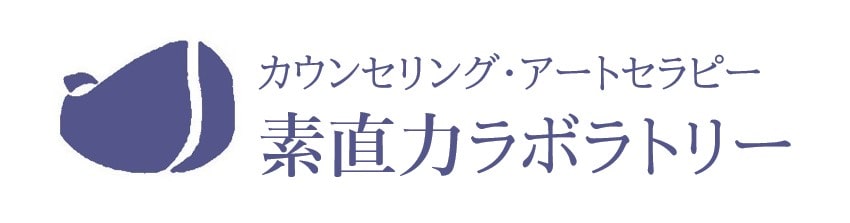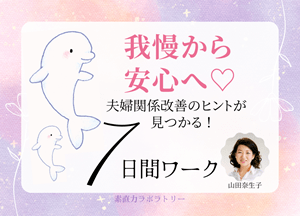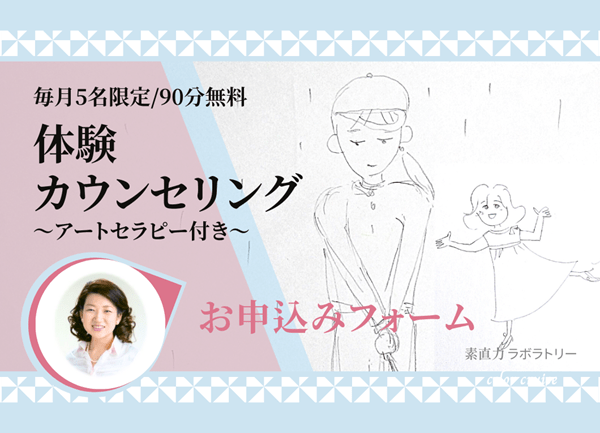子どもが嘘をつく理由とは?年齢別に見る心理と親ができる関わり方
はじめに
「うちの子、また嘘をついた……」
そんなふうに悩む親御さんは少なくありません。
「どうして嘘をつくの?」「どう接すればいいの?」と、戸惑いや不安を抱えることもあるでしょう。
けれど、子どもの嘘には、必ずその子なりの理由があります。
それを単なる“悪いこと”として叱る前に、まずはその背景に目を向けてみませんか?
実は、子どもの嘘は成長の一部でもあり、年齢や発達段階、家庭環境、性格などによって理由はさまざまです。
本記事では、子どもが嘘をつく心理的な背景を多角的に読み解き、親としてどのように寄り添い、導いていけるのかを考えていきます。
子どもが嘘をつく基本的な理由

子どもが嘘をつく理由には、いくつかの共通するパターンがあります。
理由を知ることで、子どもの心の動きが見えてきます。
そして、叱る前に「なぜそう言ったのか?」に目を向けることで、親としてより適切な対応ができるようになります。
自分の過ちや失敗を隠すため
もっとも多いのは、「怒られたくない」という気持ちからの嘘です。
たとえば、テストで悪い点を取ったときに「まだ返ってきていない」と言ったり、物を壊したのに「知らない」と言ったりするケースです。
これは、子どもなりの自己防衛反応です。
経験の少ない子どもにとって、「正直に話せばうまくいく」という発想はまだ育っておらず、目の前のピンチをしのぐことを優先してしまうのです。
特に、ふだんから厳しく叱られることが多い子ほど、この傾向が強くなります。
叱るよりも、安心して話せる関係を築くことが、嘘の減少につながります。
強い願望がつくり出す「夢のような」嘘
「今度ディズニーランドに行くんだ!」
実際は予定がないのに、そんなふうに言ってしまうことがあります。
これは、「行きたい!」という強い願望が現実と混ざって、子どもが空想を事実のように語ってしまう場合です。特に幼児期の子どもは、空想と現実の区別がまだあいまいなため、こうした嘘が自然に出てきます。
このような嘘には、悪意はありません。
むしろ豊かな想像力の表れであり、成長の一環として見守っていくことが大切です。
ただし、小学校中学年以降でもこうした嘘が頻繁に見られる場合は、「現実と願望の違い」について、丁寧に教えていく必要があります。
親の注意を引きたい気持ちからの嘘
「おなかが痛い」
「今日、先生にひどいこと言われた」
「パパが嫌い」「ママなんかいらない」
こうした言葉が、必ずしも事実とは限らない場合があります。
実はそれが、「もっと見てほしい」「構ってほしい」というサインであることも。
忙しい毎日の中で、子どもが愛情を確かめるために嘘をつく。
これは「試し行動」と呼ばれ、親の反応を通じて、自分の存在を確認しようとする行為です。
このような場合には、叱るよりも日常的に関わる時間を少しでも増やすことが大切です。
「あなたのことをちゃんと見ているよ」というメッセージが、安心感につながり、嘘の必要がなくなっていきます。
相手を心配させたくない思いやりの嘘
「学校どうだった?」「うん、楽しかった」
でも実は、友達とトラブルがあって落ち込んでいた――そんなこともあります。
子どもはときに、親を心配させたくない、悲しませたくないという気持ちから、あえて本当のことを言わないことがあります。
これは、子どもなりのやさしさや気遣いの表れでもあります。
とはいえ、問題をひとりで抱えてしまわないように、
「本当のことを言っても大丈夫だよ」
「話してくれてありがとう」
そんな安心できる関係づくりが大切です。
年齢・発達段階別の嘘の特徴

子どもの嘘は、「悪いこと」と一言で片づけられるものではありません。
年齢や発達段階に応じて、その意味や背景は大きく異なります。
子どもがどんな時期に、どんな気持ちで嘘をついてしまうのか――それを知ることは、子育てにおいてとても大切な視点です。
幼児期(2歳半~5歳):空想と現実の境界があいまい
この時期の嘘は、「嘘」というより空想の延長線であることが多いです。
- 「昨日、空を飛んだ夢を見た」→「昨日、本当に空を飛んだんだよ!」
- 「おばけに怒られた」
- 「プリンセスとお友達になった」
など、願望や想像をそのまま口に出してしまうのが特徴です。
2〜3歳ごろは、現実と想像の区別がまだ曖昧で、意図的に嘘をついているわけではありません。
4〜5歳になると、「バレなければ大丈夫」という考えが出始め、怒られたくない・恥ずかしいといった気持ちからの意識的な嘘が見られるようになります。
この時期の嘘は、「正直に話しても大丈夫」という安心感を育てることで、少しずつ減っていきます。
学童期(6歳〜12歳):自尊心とプライドが生まれる時期
小学校に入ると、子どもの嘘はより目的がはっきりしてくるようになります。
- 「宿題は終わった」→本当はまだだけど、遊びたくて言ってしまう
- 「先生にほめられた」→少しだけ注意されたけど、見栄を張りたかった
- 「友達にいじめられてる」→本当は1人でいるのが寂しかっただけ
この時期の子どもは、「失敗=恥ずかしいこと」と捉えやすく、失敗や劣等感を隠そうとする嘘が増えます。
また、友達関係のトラブルや、親の期待とのギャップに苦しんで、「本当の気持ちを言えない」という状況が嘘につながることも。
大切なのは、失敗しても受け入れられるという体験を通して、「正直でいるって気持ちいい」と思えるように導いていくことです。
思春期(13歳〜):自立と葛藤の中で生まれる複雑な嘘
思春期に入ると、子どもの嘘はより巧妙かつ心理的な距離を取るためのものになっていきます。
- 「学校、別に普通だった」→本当は友達関係に悩んでいる
- 「スマホなんて見てない」→夜遅くまでこっそり使用していた
- 「大丈夫、心配しないで」→実は不安や孤独を抱えている
この時期の嘘の裏には、
- 親に心配をかけたくない
- プライドを守りたい
- 自分の世界に踏み込まれたくない
といった、大人に近い心理的背景があります。
親としては、「嘘をつかれた」と責めるよりも、「本音を言える雰囲気をつくること」が求められます。
干渉しすぎず、放任しすぎず、「信じているよ。でも、困ったときはいつでも話していいよ」というスタンスが信頼関係の土台となります。
中学生特有の嘘:揺れる自己評価と対人関係の葛藤
中学生になると、さらに具体的で戦略的な嘘が見られるようになります。
以下はよくある5つのパターンです。
- 叱られたくない嘘
→ テストの点数をごまかす、帰宅時間をずらすなど。「言ったら怒られる」と思ってしまう背景あり。 - 承認欲求からの嘘
→「〇〇点だった」「告白された」など、見栄を張ることで自分を大きく見せたがる傾向。 - 友人関係のための嘘
→本当は嫌だけど「うん、いいよ」と言って合わせる/仲間外れを避けるために嘘をつく。 - 親の話を流してしまう嘘(受動的な嘘)
→「わかった」「やった」と返事をしておきながら実際はやっていない。関係が希薄になっているサインの可能性も。 - 「どうせわかってもらえない」という諦めからの嘘
→親子の会話がうまくいっていない場合、信頼関係の不足が嘘を習慣化させてしまうことがあります。
子どもが嘘をつくとき、それは心の中に何らかのサインがあるということ。
年齢や発達段階によって、嘘の質も目的も異なります。
大切なのは、「嘘をなくす」ことではなく、
「なぜこの子は嘘をついたのか?」を見つめて、安心して本音を言える環境をつくることです。
家庭環境と嘘の関係

子どもが嘘をつく背景には、家庭での関わり方や雰囲気が深く関係しています。
「なぜこの子は嘘をついてしまうのか?」という問いに向き合うとき、子どもだけではなく、家庭のあり方にも目を向けることが大切です。
健全な家庭環境を整えることは、子どもが安心して本音を話せる土台をつくり、結果として嘘が減っていくことにもつながります。
親子の信頼関係が、正直さの土台になる
子どもが嘘をついてしまう大きな理由のひとつが、「本当のことを言ったら怒られるかもしれない」という不安です。
- 「怒られたら嫌だから、黙っていよう」
- 「どうせわかってもらえないから、本当のことは言わないでおこう」
そんな気持ちが積み重なると、子どもは次第に本音を隠すようになります。
親子の信頼関係を築くには、
まずは、子どもの話を最後まで否定せずに聞くことが基本です。
そして、たとえ困る内容だったとしても、「正直に話してくれてありがとう」と伝えること。
その一言が、子どもに「本音を言ってもいいんだ」という安心感を与えてくれます。
厳しすぎる子育ては「嘘で自分を守る」クセをつくる
完璧を求めすぎる親の姿勢や、日常的に強く叱られる家庭環境では、
子どもは「本当の自分では愛されない」「失敗は許されない」と感じ、嘘を使って自分を守ろうとするようになります。
- 成績や態度を隠す
- できていないことを「できた」と言う
- 理想の子ども像に合わせるために演じる
こうした嘘の背景には、ありのままの自分では受け入れてもらえないという不安が潜んでいます。
子どもの成長には、失敗や試行錯誤も大切な学びの一部です。
小さな失敗にも「それも経験だね」「正直に言えてえらいね」と寄り添うことで、
子どもは次第に「嘘をつかなくても大丈夫」と感じられるようになります。
親の姿が子どもへのメッセージになる
子どもは、親の言動をよく見ています。
親が日常的に小さな嘘をついていると、子どもはそれを「普通のこと」として覚えてしまいます。
たとえば——
・電話に出たくないときに「お母さん、いませんって言って」
・本当は気が進まないだけなのに「今日は用事がある」と断る
・子どもとの約束を忘れてしまっても、ついごまかしてしまう
こうした場面は、誰にでもあるものです。ですが、それが繰り返されると、子どもは
「本当のことは言わなくてもいいんだ」
「大人も嘘をつくものなんだ」
と、学習していきます。
大切なのは、嘘をつかない“完璧な親”になることではありません。
事情があって約束が守れないときは、きちんと説明して、素直に「ごめんね」と謝ることで、子どもは「誠実さ」を学びます。
親が「嘘をつかずに向き合おうとする姿」を見せることが、子どもにとって何よりの教材になります。
コミュニケーション不足が「嘘で気を引く」きっかけに
近年、共働き家庭の増加などにより、親子で過ごす時間が減っていることも、子どもが嘘をつく背景にあると言われています。
- 「今日は学校で嫌なことがあった」と言えば、親が話を聞いてくれる
- 「お腹が痛い」と言えば、そばにいてくれる
そんな体験から、「嘘をつけば構ってもらえる」と学んでしまうことがあります。
また逆に、「忙しそうだから言わないでおこう」「心配かけたくないから隠しておこう」と、親に遠慮して本当のことを言わない子もいます。
こうした状況を防ぐためには、量より質のコミュニケーションが鍵です。
- 短時間でもいいので、目を見て話を聞く
- 子どもの話を途中で遮らずに、最後まで聞く
- 「今日どうだった?」ではなく、「今日はどんな気持ちだった?」と聞く
こうした丁寧な関わりを日々積み重ねることで、子どもは「本当のことを言ってもいい」「親は自分のことを見ていてくれる」と感じられるようになります。
子どもの嘘にどう向き合う?

叱る・見逃すの判断と、再発を防ぐ関わり方
子どもの嘘にどう対応するかは、親にとって悩ましいテーマです。でも、適切な対応を知っていれば、嘘の再発を防ぎながら、子どもの心の成長もサポートできます。
大切なのは、感情的にならず、子どもの気持ちに寄り添いながら対応することです。
叱るべき嘘、見逃してもいい嘘
すべての嘘を同じように叱る必要はありません。
まずは、子どもがついた嘘の「背景」を見ていくことが大切です。
叱るべき嘘とは、
・他人を傷つけるための嘘
・重大な失敗や問題を隠そうとする、悪質な嘘
社会性を育てるうえでも、このような嘘には「なぜいけないのか」をしっかり伝えましょう。
一方で、見逃してもいい嘘もあります。
たとえば、
・親の気を引きたくてついた嘘
・心配をかけたくないという思いやりからの嘘
こうした嘘の背景には、「寂しさ」や「優しさ」などの感情が隠れていることもあります。
この場合は叱るよりも、気持ちをくみ取ってあげる関わりが大切です。
「ママ(パパ)は、あなたの気持ちをわかろうとしてくれている」
子どもがそう感じられると、次第に正直に話してくれるようになります。
感情的にならないための工夫
嘘をつかれると、つい感情的になってしまうものですよね。
でも、その反応が子どもをさらに萎縮させ、嘘をエスカレートさせてしまうことも。
まずは一呼吸おいて、冷静になってみましょう。
子どもの嘘を「自分への裏切り」と受け取るのではなく、
「この子は、なぜそう言ったのかな?」と背景を探る視点に切り替えてみてください。
嘘を指摘する場面でも、「あなたは嘘つきね」とレッテルを貼るのではなく、
「今の話、本当かな?」とやんわり確認する程度にとどめるのがポイントです。
そして、子どもが正直に話してくれたときは、
必ず「本当のことを話してくれてありがとう」と伝えましょう。
子どもの気持ちをくみ取る声かけ
子どもの嘘の裏には、きっと何か理由があります。
「どうしてそう言ったのかな?」と優しく尋ねてみてください。
怒りや否定ではなく、「理解したい」という気持ちが伝わると、
子どもも安心して本音を話しやすくなります。
たとえば――
「心配かけたくなかったんだね」
「怒られるのが怖かったのかな?」
と共感を示しつつ、最後に
「でも本当のことを教えてくれて、うれしかったよ」
「正直に言ってくれると、ママ(パパ)は安心するな」
と伝えていきましょう。
「正直に話しても大丈夫なんだ」という体験が、子どもを変えていきます。
再発防止のための環境作り
子どもが嘘をつかなくてもすむ環境を、親が整えてあげることも大切です。
・失敗しても責めない
・完璧でなくても認めてもらえる
・どんな話でも最後まで聞いてもらえる
そんな「安心できる家庭」は、嘘より本音を選べる土台になります。
親自身が、
・感情的にならずに話す
・子どもとの約束を守る
・普段から一対一の時間をとる
こうした関わりを積み重ねることで、
「どんなことでも話して大丈夫」という信頼が育まれます。
まとめ
子どもが嘘をつく理由は、本当にさまざまです。
年齢や発達段階、家庭環境、性格などによって、その背景は一人ひとり違います。
大切なのは、「嘘=悪いこと」と決めつけるのではなく、その奥にある子どもの気持ちをくみ取ろうとする姿勢です。
多くの子どもは、「怒られたくない」「嫌われたくない」「わかってほしい」といった気持ちから嘘をついています。
それは、自分を守りたいという心のサインでもあるのです。
だからこそ、親はまず冷静になり、子どもが安心して本音を話せるような関係をつくることが大切です。
正直でいることの大切さを伝えるには、親自身が日々の中で誠実な姿を見せること。
約束を守ること、できなかったときは謝ることも、子どもにとっての「大切な学び」になります。
子どもの嘘もまた、成長のひとコマ。
大人の関わり方しだいで、子どもは信頼や誠実さを育んでいくことができます。
よくある質問
なぜ子どもは嘘をつくのですか?
子どもが嘘をつく背景には、実にさまざまな理由があります。たとえば、「怒られたくない」「失敗を隠したい」「自分の願いを通したい」「親の関心を引きたい」「相手を心配させたくない」など、子どもなりの事情や気持ちがあります。また、発達段階によっても嘘の傾向は異なり、年齢が小さいほど、想像と現実の区別がつきにくいこともあります。子どもの嘘には、必ず何らかの理由があると理解することが大切です。
子どもの嘘にどう対応したらいいですか
まずは感情的にならず、冷静に子どもの気持ちをくみ取ることが大切です。すべての嘘を一律に叱るのではなく、「叱るべき嘘」と「見守るべき嘘」を見極める視点が必要です。子どもが「正直でいても受け入れてもらえる」と感じられる環境を整えることが、嘘を減らす第一歩です。また、親自身が誠実にふるまう姿を見せることも、子どもへの良い手本になります。
家庭環境は子どもの嘘に影響しますか?
はい、大きな影響があります。たとえば、親が日常的に嘘をついていたり、子どもとの約束をよく破ったりしていると、それを見て育った子どもも自然と嘘を覚えてしまいます。また、厳しすぎるしつけや、「失敗は許されない」という空気が強い家庭では、子どもが本音を隠そうとして嘘をつくこともあります。親子の信頼関係が土台となり、子どもが安心して、本音を話せる雰囲気づくりがとても大切です。
🌸 「この記事、ちょっと当てはまるかも…」と思ったあなたへ 🌸
ひとりで抱えず、話してみませんか?
ランキングに参加しています。